社長ブログ
BLOG

ラルズネット奨学金返還支援制度
こんにちは!鈴木です。
社内ごとではありますが、10月から「ラルズネット奨学金返還支援制度」という取り組みを始めます。これはひとことで言えば、「社員が抱えている奨学金の返済残高を、当社も一緒に払っていきます」というものです。
勤続10年目までの社員については、月の返済額のうち毎月1万円分を当社が代わりに負担し、11年目以降の社員については、月の返済額の全額を当社が負担する(その社員はもう何も払わなくて良い)という内容になります。
似たような制度を取り入れている他社の事例を見ると、「支援総額は最大120万円まで。支援期間は最長5年まで」といった上限を設けているケースが多かったのですが、当社は思いきって上限を設けないことにしました。
つまり、たとえ返済残高500万円・返済期間20年の場合であっても、その社員が在籍する限り完済まで支援していくということです。
今や大学生・専門学校生のおよそ2人に1人が奨学金制度を利用しており、労働者福祉中央協議会のアンケート調査によると、平均借入総額は310万円、返済期間は14.5年、そして「返済負担が苦しい」と回答した人が44.5%にまでのぼっています。
この負担は、結婚・出産・子育てなど、その後の人生の重大イベントにまで影響を及ぼしています。
今回の制度は、このような社会的課題の解決と、社員が安心して長く働ける職場づくりの両方に寄与できるのではないかと思い、新設した次第です。
▼詳細はこちら
プレスリリース:株式会社ラルズネット、社員の奨学金を返済完了まで代理返還する【奨学金返還支援制度】を導入 勤続11年目以降の社員には全額支援も

死に物狂いで頑張った大学受験
私自身、奨学金をたくさん借りて乗り越えた過去があります。大学に3つも行ったのです。
高校時代は友人と遊ぶのが楽しく勉強をサボりすぎて、成績は全生徒中下から5番目くらい。
その後、とくに勉強もせず入れる地方の大学に行き、ダラダラと過ごす毎日。四畳半の古アパートで天井を見上げていると、なんだかパッとしない人生だなと思い、数ヶ月で退学。
そこから心機一転、勉強しまくり東京の大学を目指します。結果、自分なりに頑張ったのですが点数が届かず第一志望は不合格。
もうこれ以上、勉強漬けの日々は耐えられないと思い、また自分に妥協して、希望とは関係のない大学に入ることにしました。しかし、案の定、楽しいわけもなくモヤモヤした気持ちを引きずりながら、月日だけが経過していきます。
そんな自分に嫌気が差し、二度目の退学を決意します。いわば2浪。またイチから全部やり直しです。ここで大きな気付きを得ます。それは「保険で逃げ道をつくっても意味がない」ということです。人の目はごまかせても、自分の心はごまかせません。
3回目の受験は滑り止め校は一切選ばず、退路を絶って朝から晩まで(成人式も行かず)死に物狂いで勉強し、希望校になんとか合格することができました。
私はこの体験から、「困難に立ち向かうことよりキツいのは、困難から逃げ続けること」だと、身をもって知ったのです。
何年か遠回りをし、借りた奨学金も大きな額になりましたが、このときの経験は社長業をやっている今でも確実に生きていて、とくに苦しい局面での精神的支柱として自分の中にしっかりと残っています。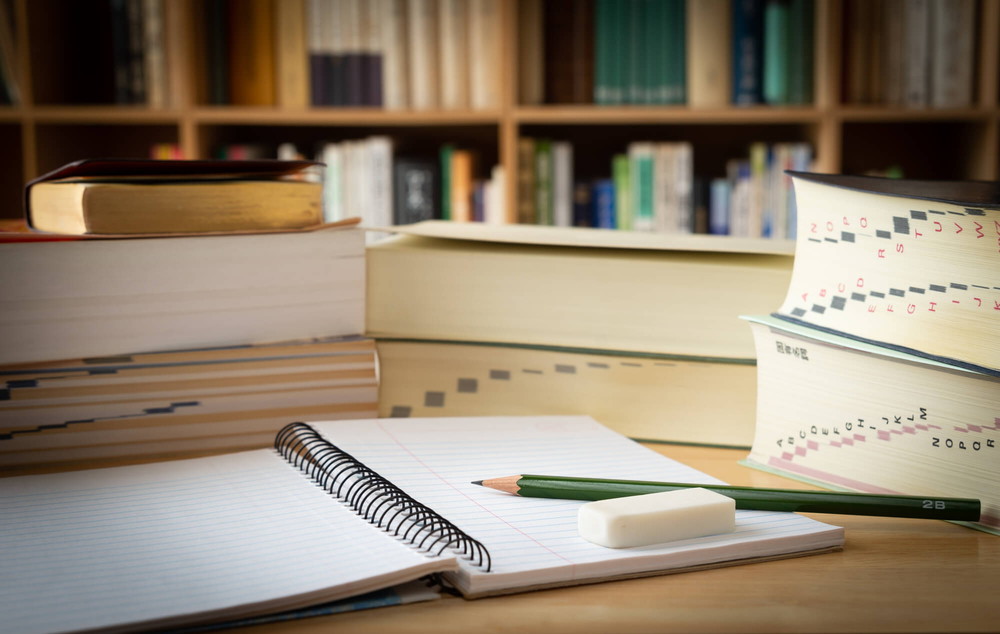

鈴木 太郎
(株)ラルズネット代表取締役社長。函館市出身。2006年明治大学卒業。宅建士資格を取得し、野村不動産ソリューションズ(株)入社。不動産仲介(法人営業)に携わる。その後、講師職を経て2010年当社入社。営業部にて制作事業の売上を3倍にリード。2013年同社GM就任。同年、総売上最高値更新。2014年同社常務取締役就任。営業、商品企画、経営戦略を担当。2020年から現職。
最新記事
仕事としての健康
健康は社員と家族を守るための仕事 こんにちは!鈴木です。 今回は「仕事としての健康」というテーマでお伝えします。 「健康も仕事のうち」という言葉が、経営者ほど当てはまる職種もありません。学生の必修科目

経営者が持つ「本気モード」
逃げ道がないから覚悟が決まる こんにちは、鈴木です!2025年を振り返ると「本当によかった」と思える社内トピックスが2つあります。 1つ目は、提供から10年以上経った不動産会社様向けシステム『ラルズマ

企業を強くする情報発信
各ステークホルダーが求めるもの こんにちは、鈴木です! 今回は、「企業における情報発信の重要さ」についてお話しします。 企業が情報発信する相手は、主なステークホルダー、つまり「お客様、社員、銀行、株主

ラルズネットが目指すのは、
不動産会社様のための「成長コミュニティ」です
サービスに関する詳細・ご相談はこちら
不動産システム


最小の手間で、最大の反響を。物件登録・反響管理・物件チラシ作成などを一元化できる業務支援システムです。AI・自動アドバイス機能搭載。
不動産システム


最小の手間で、最大の反響を。物件登録・反響管理・物件チラシ作成などを一元化できる業務支援システムです。AI・自動アドバイス機能搭載。
お電話でも受け付けております
ラルズネット サポートセンター
0120-071-036〈受付時間〉9:00-18:00(土日祝除く)











