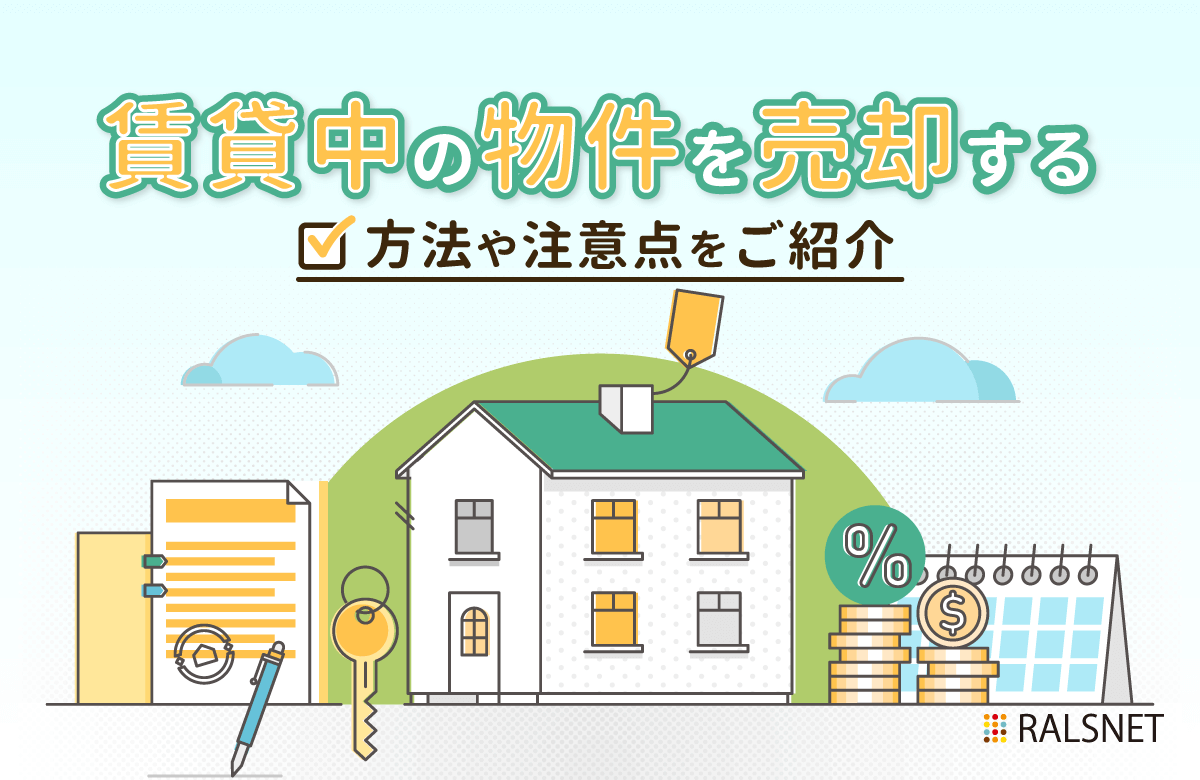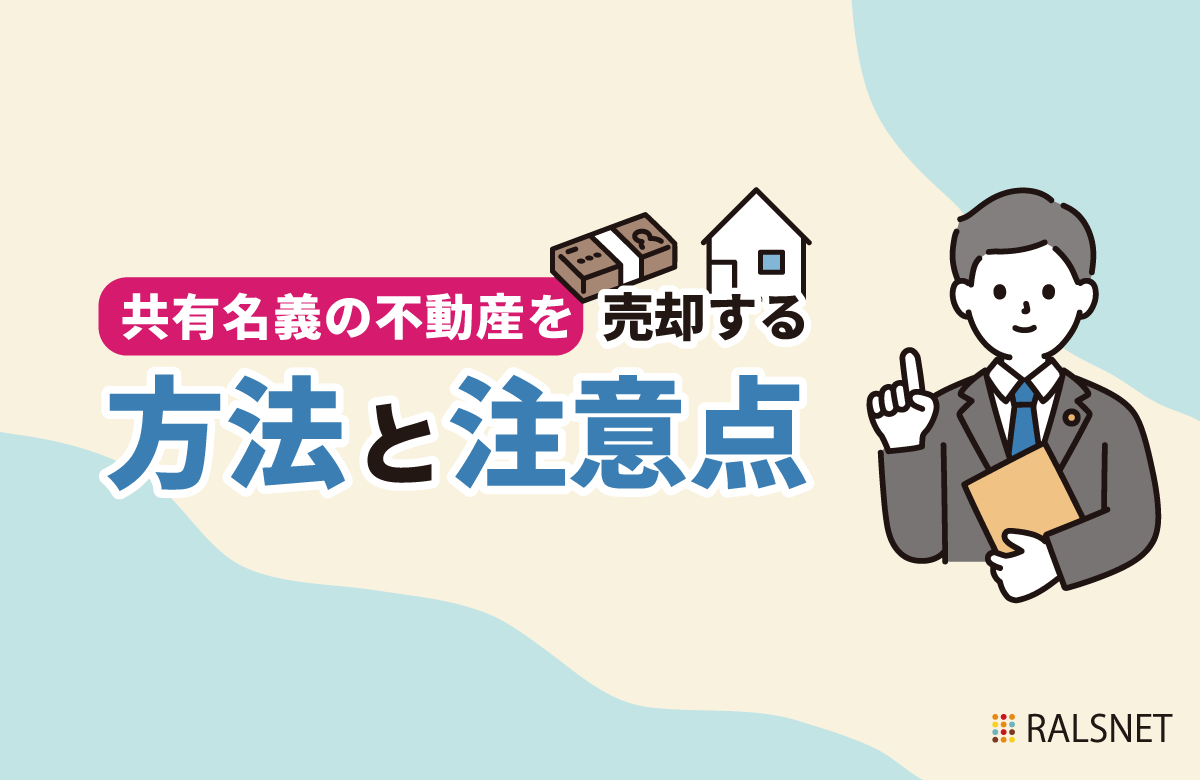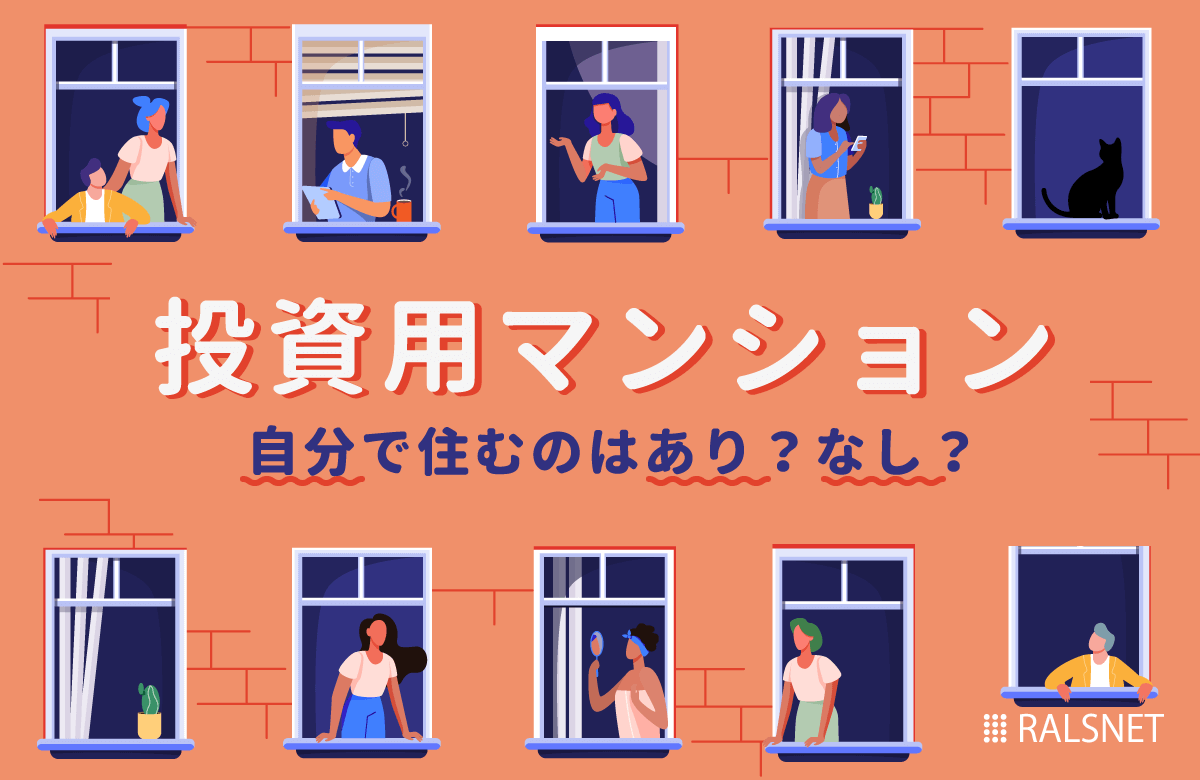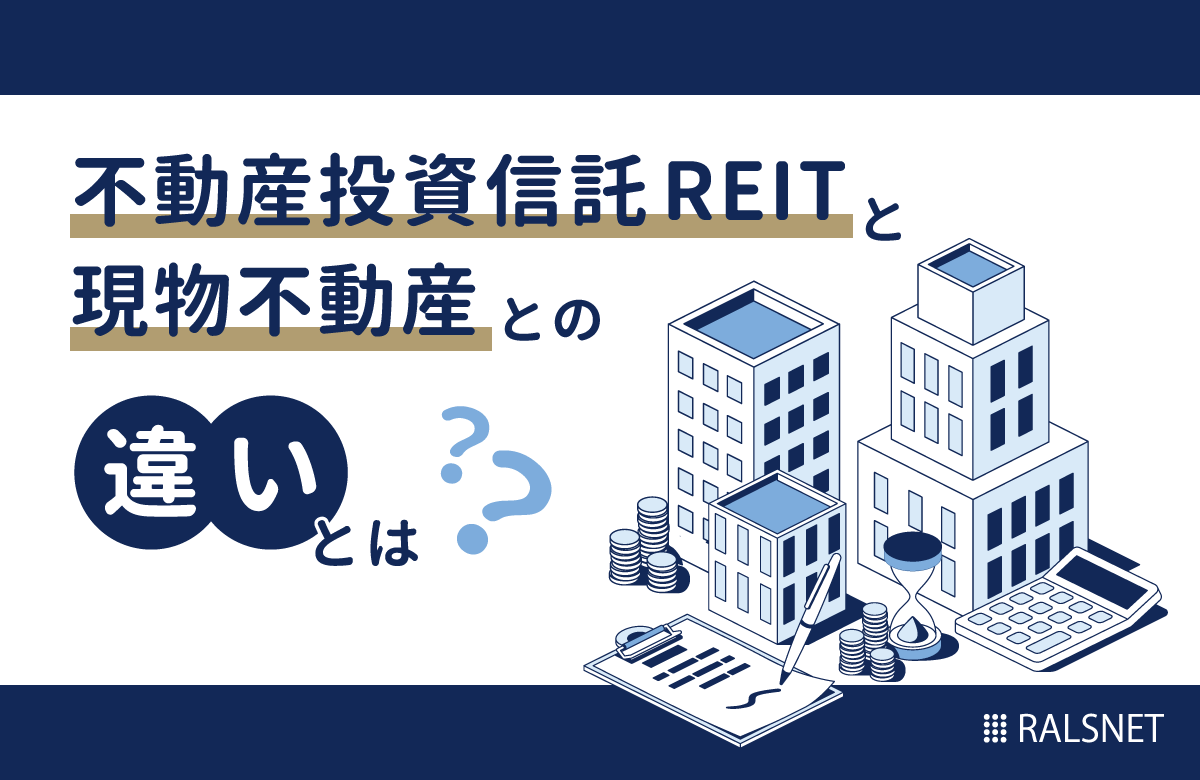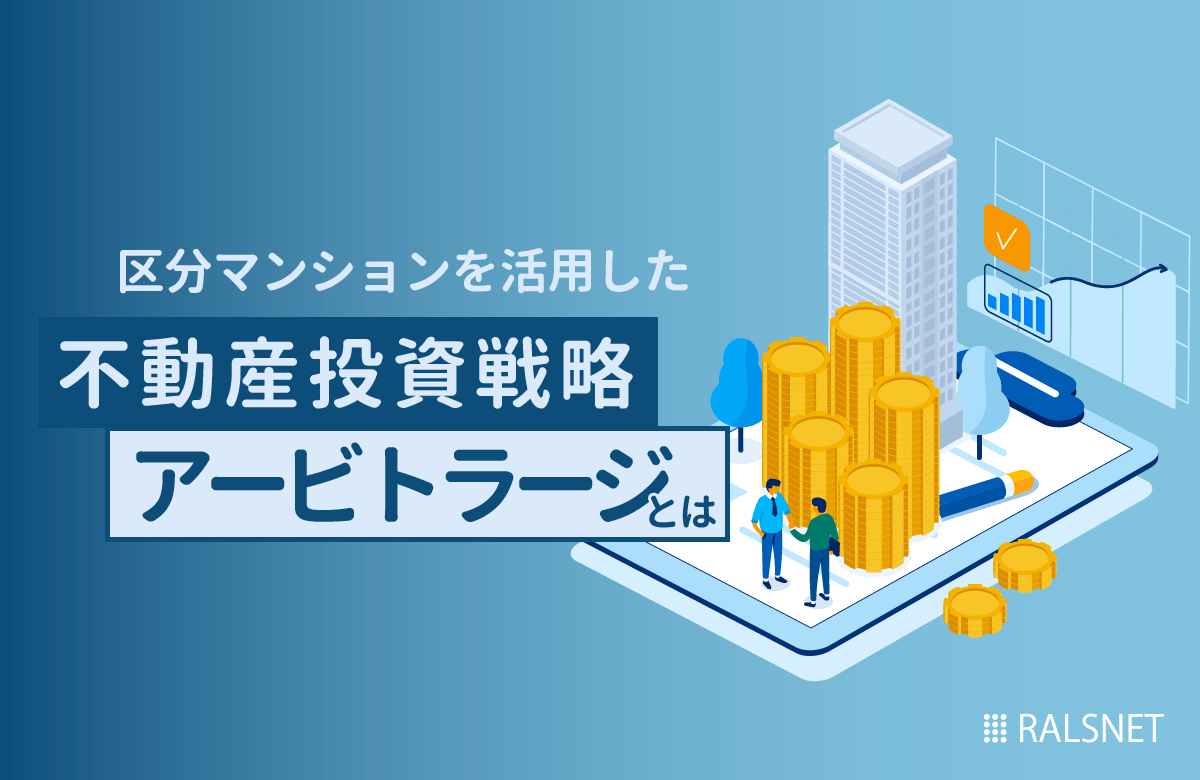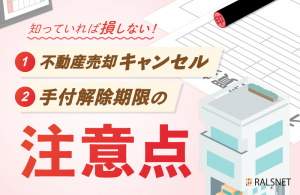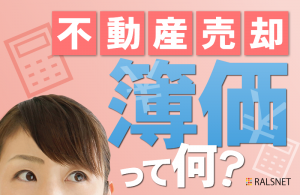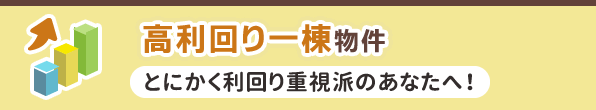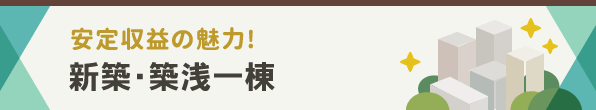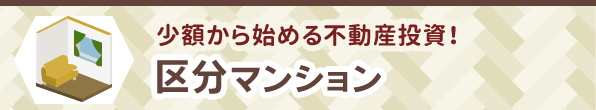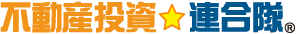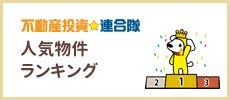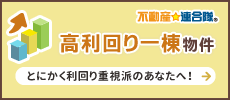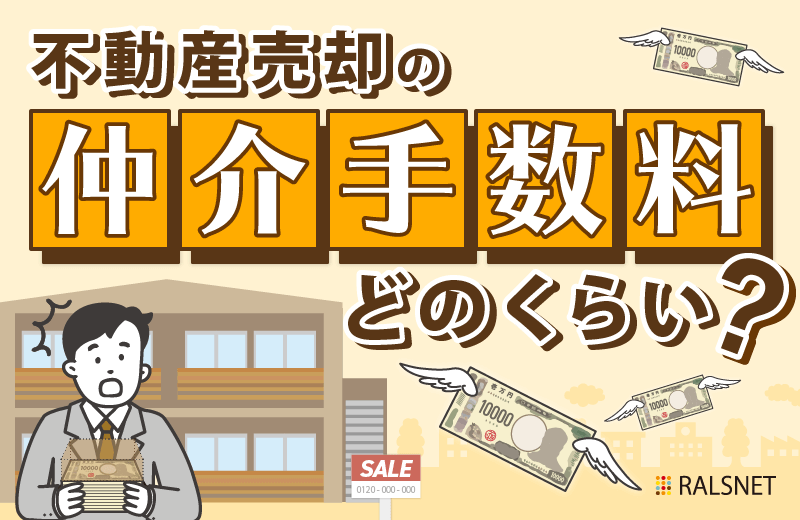
投資用不動産の売却を検討する際は、物件の成約価格だけではなく、売却時に発生する諸費用についても考慮しておく必要があります。
特に仲介手数料は決して無視できる金額ではないので注意が必要です。
この記事では、不動産売却時に必要な仲介手数料がどれくらいかかるのかを詳しく解説していきます。
不動産売却時に掛かる仲介手数料とは何か

直接取引などを除けば、投資用不動産の売却は不動産仲介業者に依頼することが一般的です。
その際は、仲介業者と「媒介契約」を結び、仲介業者は宣伝や広告、既存顧客への案内などの売却活動を行うことになります。無事成約した場合、売主は仲介業者に成功報酬を支払います。この報酬が「仲介手数料」です。
仲介手数料の金額については宅地建物取引業法で上限が定められており、成約価格が400万を越える場合は、成約価格の3%+6万円となっています。
これはあくまでも「上限」であるため、仲介業者との間で値引き交渉をする余地はあります。
しかし、大手の仲介業者は仲介手数料の値引きには応じないことが一般的なので注意が必要です。
ただし、あまりに規模の大きい取引などの場合は別です。なお、媒介契約には「一般媒介契約」「専属専任契約」などの種類がありますが、どの契約を結んだ場合でも、仲介手数料は変わりません。
また、投資用、居住用、土地、建物といった違いもありません。
売却価格ごとの仲介手数料の計算方法
仲介手数料の上限は、売却価格によって料率が変わります。あくまで成約価格を基準にするため、査定額や売出価格などは関係ありません。
価格帯は「200万円」「400万円」が区切りとなっています。
都市部の投資用物件では400万円未満の物件は極めて限られていますが、郊外のワンルームなどでは頻繁に取引される価格帯です。間違いのないように確認しておくことが必要です。
では、それぞれの価格帯の計算例をみてみましょう。
売却価格が200万円以下の場合(上限5%)
料率の上限は5%と決められています。例えば売却物件の成約価格が「150万円」で料率が「5%」の場合、「150万円×5%」となり、仲介手数料は「7万5千円(+消費税)」となります。
売却価格が200万円~400万円以下の場合(上限4%+2万円)
料率の上限は4%+2万円と決められています。例えば売却物件の成約価格が「300万円」で料率が「4%+2万円」の場合、「300万円×4%+2万円」となり、仲介手数料は「14万円(+消費税)」となります。
売却価格が400万円を超える場合(上限3%+6万円)
料率の上限は3%+6万円と決められています。例えば売却物件の成約価格が「2,000万円」で料率が「3%+6万円」の場合、「2,000万円×3%+6万円」となり、仲介手数料は「66万円(+消費税)」となります。
仲介手数料の「+2万円」や「+6万円」などはどういう意味か

不動産の取引は、物件によってかなり金額に幅があります。
投資物件は特に幅が広く、地方の古い木造アパートは数百万円で売買がされている一方で、都心部のビルやマンションは数億円以上であることが珍しくありません。
しかし、仲介業者にとってはどちらも同じ「1件」の取引です。そのため成約価格によって料率が変わるのは自然な成り行きですが、計算式がかなり複雑になってしまいます。
そこで、採用されたのが「速算式(法)」という計算の仕方です。
例えば成約価格が1,000万円の物件の場合は、「(200万円×5%)+(200万円×4%)+(600万円×3%)」というのが正規の計算式です。
しかし「(200万円×5%)+(200万円×4%)」の部分は、「(200万円×3%)+4万円+(200万円×3%)+2万円」=「(400万円×3%)+6万円」という数式に置き換えることができます。
そのため、「調整金額」として「+6万円」を入れることで成約価格に同じ3%の料率を掛ければよいことになり、複雑な計算をしないで済むのです。「+2万」も同じ理由です。
仲介手数料を払うのはいつ?
投資用物件の売買は、契約してすぐに引渡しができる状態のものがほとんどです。
しかし、銀行の融資などの関係もあり、契約と引渡し日が異なることが一般的です。
本来は「引渡し日に一括」でもよいのですが、「契約日に半金・引渡し日に残金」という支払い方が不動産業界の慣例となっています。
これは国土交通省(当時の建設省)の行政指導のなごりです。法的には「どちらでも可」ということになっています。
逆に、合意のもとで「契約時に一括」で支払ってしまうことも可能です。
ただし、借地権などにからんだ「停止条件付契約」の場合は、この限りではありません。
地権者の承諾が得られるまでは契約成立とは認められないため、売買契約を締結した時点では仲介業者の報酬請求権がまだ発生していないからです。
仲介手数料の意義を考え、賢い売却活動を
このように、仲介手数料に関しては多くの規則があり、内容もやや複雑な部分があります。
しかし、物件の売却をする上では必ず押さえておく必要があります。
投資物件の売却はさまざまな法的責任を伴うため、トラブルを防止するためには取引実績の豊富な信頼できる仲介業者に売却を依頼することが大切です。
適切な仲介手数料を理解した上で、総合的に仲介業者を判断して選びましょう。
関連するキーワード
この記事に関連するキーワード
合わせて読みたい!「出口戦略」に関するコラム 「出口戦略」に関するコラム
![賃貸中の物件を売却する方法や注意点]()
出口戦略2023/05/02
賃貸中の物件を売却する方法や注意点
, , , ,
![共有名義の不動産を売却する方法と注意点]()
出口戦略2023/03/10
共有名義の不動産を売却する方法と注意点
, , , , ,
![不動産売却をする際に必要な委任状の注意点]()
出口戦略2023/01/10
不動産売却をする際に必要な委任状の注意点
, , , , ,
不動産投資を学ぼう!新着コラムをチェック 新着コラムをチェック!
![投資用マンションに自分で住むのはあり?なし?]()
物件購入2023/09/05
投資用マンションに自分で住むのはあり?なし?
, ,
![不動産投資信託REITと現物不動産との違いとは]()
物件購入2023/08/01
不動産投資信託REITと現物不動産との違いとは
,
![区分マンションを活用した不動産投資戦略アービトラージとは]()
物件購入2023/07/04
区分マンションを活用した不動産投資戦略アービトラージとは
, , , ,
投資物件を探してみよう!powered by
一棟売り物件
- さらに一棟売り物件を見る
- 満室時 想定利回り 20%以上の一棟
- 仲介手数料無しの一棟
- 現在満室の一棟
- 満室時 想定利回り 20%以上の一棟
- 仲介手数料無しの一棟
- 現在満室の一棟
区分所有物件
- さらに区分所有物件を見る
- 300万円以下の区分
- 500万円以下の区分
- 800万円以下の区分
- 1,000万円以下の区分
- 〜300万円
- 〜500万円
- 〜800万円
- 〜1,000万円